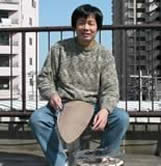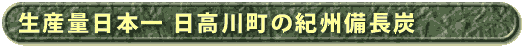
和歌山県中部を流れる清流 日高川
この日高川周辺で生産された紀州備長炭をお届けしています。


原木を伐採する天然林 とても険しい山が多いです。
紀州備長炭の原木は再生されるので森林破壊になりません。
江戸時代から何回も伐採され、再生しています。
紀州備長炭の代表的な原木、ウバメガシは紀伊半島の比較的沿岸部に近い、温暖な山林に自生しており、生産者はその山に近い位置に炭焼き窯を置いています。
和歌山県が主体ですが一部、奈良県でも生産されています。
生産者は互いに協力できるよう、ある地域に集中して窯を設けることが多いです。
日高川町は、2005年に川辺町・中津村・美山村が合併してできた町で、もともと生産量2位の中津村を含むこともあり、南部川村の生産量を抜いて、紀州備長炭生産量日本一の町となっています。
生産者について
直接仕入れ
紀州備長炭本舗の備長炭は、全て生産者から直接仕入れを行っています。
問屋さんを通さず低価格で提供するため、そしてオリジナル(特別規格品)をお届けするためです。
ただ、そのためまだまだ在庫量が少なくすぐに品切れがおこりますので、なるべく多くの生産者から仕入れる努力をしております。
日高川町 12名の生産者
和歌山県日高川町の生産者12名(2007年現在)の皆様にご協力いただいています。
旧中津村(三十位川地区)、大滝川、山野、大又、といわれる地域などの生産者です。
※今後はもっと協力者を増やしてまいります。
なぜ12名も・・・
当店の備長炭は個人宅で使用できる限られた長さ、大きさのものばかりです。
業務用は20~50cmの長さがあり、家庭ではカットが困難で使いにくいものです。
しかも、細かく割れたり、乱雑に割れたものを含まない、紀州備長炭本舗特有の指定規格品です。
そのため、一度の生産工程でわずか1/20~1/30ほどしか生産できないので、
多くの生産者にご協力いただかないと皆様に供給できないのです。

生産者から引き取った備長炭は
一端倉庫に集めてから大阪に運びます。
窯と製炭について
紀州備長炭の窯(かま)
紀州備長炭の窯は、道路横の山の傾斜地を利用して作られていることがほとんどです。
傾斜地を削ってつくることで、窯が土に覆われ断熱効果が高くなると共に、頑丈な窯を作りやすいためです。
道路横にあるのは、何と言っても原木の運搬を優先させるためで、窯の横に車が横付けできないと仕事にならないのです。
台風で屋根がぶっ飛んだり、大雨で浸水したり、自然との闘いも多いです。
窯だしの日など徹夜作業も多いので、食事や休憩のできる小屋や納屋が隣接されています。生産者の自宅がすぐ近くにあることも多いですが、窯は煙と灰の舞い上がりがひどいので、人家とは少し離れています。



窯の構造
窯は、土と瓦、石積みにより作られ、代々受け継がれた伝統的なものです。
窯の製作技術は紀州備長炭の製炭技術の最たるもので、窯によって備長炭の品質が左右される重要なものです。
それぞれの生産者によって、形状や作り方も異なります。


(左)新品の窯 (右)窯を補修を重ねて7年ほど使用したもの
一度に500kgほどの備長炭が窯から出されますが、窯の大きさは生産者の体力や仕事のペースによって調整されておりさまざまです。

人が通りやすいように。
縦長の入口になってます。


(左)窯の奥の空気を吸い取るための口
(右)ドーム型屋根の後の排煙ここに煙突がつながります。

この入り口の空気穴と後ろの煙突による排煙によって
酸素供給を調整します。

窯の上部はドーム型に作られます。
若い人の窯は、高い技術をもった生産者に
技術指導をうけながら共同で作られることが多いです。

使用する土は現地特有のもで、
土の調達方法なども学ばないと窯が作れません。


内部を木組でささえてドーム型の天井が作られます。
この木組みは燃やされてなくなります。
日高川町製炭研修所


紀州備長炭の製炭技術を学ぶための、町営の炭焼き窯です。 地方から転居してきた人の多くがこの研修窯の卒業生で、これから紀州備長炭の生産者を目指す人は、ここで数ヶ月間の修行を経て、自分の窯を持ちます。 ベテランの製炭師が自分の仕事もこの窯でこなしながら、人材育成にあたっておられます。
製 炭
伐採された原木は、窯に立てて入れられます。隙間なく入れるため曲がりくねった原木にチェーンソーで切り目を入れ、真っ直ぐに伸ばして入れます。
太い原木は2分割、4分割に割って入れます。

窯へ入れる前の原木
原木に切り目を入れて真っ直ぐに伸ばします。
窯の屋根はドーム型で場所により天井高が違うため原木も長さを変えて切ってあります。
原木は乾燥させるとよい備長炭にならないので、伐採後はなるべく早く窯に入れなければなりません。

原木を入れると口火を焚いて、窯の温度を少しづつ上げていきます。
原木の水分を飛ばしながら、酸素をほとんど与えず、高温で蒸し焼きにします。
完全に炭化すると、空気を送り込んで燃焼させます。
これを「精錬」といい、これによって樹液の成分は完全になくなり、引き締まって比重の大きい炭になります。黒炭はこれを行わず、窯を密閉して冷却させますが、備長炭(白炭)は燃え盛る炭を窯の外で消します。

窯出し
原木れてからを入、11日ほどで「窯出し」を向かえます。

窯出しは時間に追われる作業なので、2、3人で行うことが多いです。
生産者は窯出しのタイミングを調整して、お互いに助け合いながら行うことが多いです。
窯から出した備長炭は、折らないように丁寧に灰の上に置かれます。

水分を含ませた灰と土を混合させた「素灰:すばい」をかけて消火させます。
この灰が炭の表面に付着して白っぽく見えることから、「白炭」といわれます。
白炭にはさまざまあり、紀州備長炭も「白炭」の一種です。

形状により細かく分類して箱詰めされ出荷されます。
生産者により専属の炭問屋さんが決まっています。
最大手はJA(農協)さんですが、その他にも数軒の炭問屋さがあります。
上小丸、小丸、中丸、細丸、乙細丸、半丸、切小丸、荒上、荒並、割、など10種類ほどに細かく分類して、箱に詰めます。分類は問屋さんによっても異なります。

業務用は15kg箱に入れられて出荷されます。 箱は炭問屋さんの名が入った箱と町村単位の生産者の会で作られた箱の2種類があります。
上:地域の生産者の会の箱(日高川町の箱)
下:JAさんなど炭問屋さんの箱
原木の調達
原木は山中に入り、「自分で伐採する」方法と、原木伐採専門の業者さんから「買い取る」方法の
2つがあります。自分で伐採した方が利益を得やすいので、体力のある人は自分で伐採し、
お年寄りや近くで伐採できる山の無い人たちは業者さんから買い取ることが多いです。
また、伐採と製炭を分業し、原木は買い取って製炭に集中する生産者もおられます。
■自分で伐採
多くの生産者は自分で原木を伐採します。山中での伐採は危険で大変な労力ですが、原木の買い取り代金が不要です。


こんな急傾斜はあたりまえ。
ウバメガシは過酷な環境下で自生するので伐採は容易ではありません。
原木を切り倒し、枝を払って、いくつかに分割して運搬します。
それはとても大変な作業で、一般人なら1時間も手伝うとフラフラになります。
というか、テェーンソーをかついで山中まで登るだけでばててしまいます。
運搬
運搬は山から集材機というワイヤーケーブルで滑車を滑らせて下ろす方法、レールを敷いたモノラックという小さなトロッコで運ぶ方法、通称キャタピラ(バタバタ)といわれるキャタピラつきの運搬機で運ぶ方法が多いですが、その機械までは人力で運ぶしかないので大変です。夏季の熱い時期、逃げ場もなく蒸し風呂のような山中は最も厳しい仕事場となります。
また、山中に道がなければ道を作ったり、ケーブルを張ったり、と伐採に伴う大変な作業も多いのです。ケーブルを張ったり道を作るのに何週間もかかることもあるのです。
伐採権の買い取り
生産者は山林を保有しているわけではないので、山林の地主さんより原木の伐採権を買い取ります。ここからここまでの範囲で1年の伐採料が○○円、という約束で買い取ります。金額は原木の料や伐採の難易度で決めますが、明確な相場があるわけではなく、個人によりかなりの差があるようです。しかし、伐採した原木を買い取る金額よりはるかに安いようです。生産者は伐採が終わるとまた別の山を求めて移動を繰り返します。近くのよい山にめぐり合えるかどうかで、収入にも差がでるようです。
原木以外の樹木を伐採することもできますが、大木を倒すには道義上、地主さんの許可がいるようです。

2トン車に満載されたウバメガシ これから、まだまだ作業が続きます。
■原木の買い取り
原木を仕入れて製炭する生産者も多いので、ウバメガシやカシなどの原木を伐採し運搬してくれる専門業者さんがおられます。1トンあたり○万円というふうに仕入れができます。